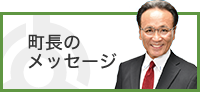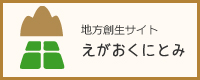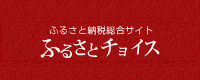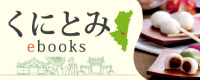サービス利用までのながれ
介護保険サービスの利用を希望する方は、「要介護認定」(注1)の申請をしてください。
申請は本人や家族が、保健介護課で直接行います。地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者(以下事業者)、介護保険施設を通して申請することもできます。
申請をする場合には、介護保険の被保険者証をお持ちください。なお、第2号被保険者の方は介護保険の被保険者証の代わりに医療保険の被保険者証が必要です。
(注1)要介護認定・・・サービス利用を希望する方が介護保険の対象となるか、またどの位の支援・介護が必要かを判定するもの
調査など
- 訪問調査
町から調査員が訪問し、心身の状況や生活の様子などについて、聞き取り調査を行い調査票を作成します。 - 主治医の意見書
訪問調査と同時に町から主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない方は町が紹介した医師の診断を受けます。
審査判定
審査・判定は、調査票や主治医の意見書、訪問調査の特記事項をもとに、介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が行います。
認定
介護認定審査会の判定に基づいて、町が要介護度の認定をし本人に文書で通知します。認定の結果は申請した日から30日程度で届きます。
サービス計画書の作成
非該当の方
地域包括支援センターで、地域支援事業などのサービス利用についてご相談ください。
要支援1・2の方
地域包括支援センターと契約し、サービス計画の作成を依頼してください。このサービス計画に基づきサービスを利用します。
作成料は全額が保険給付され、自己負担はありません。
要介護1~5の方
居宅サービスを利用する場合
居宅サービス計画を作成し、このサービス計画に基づきサービスを利用します。計画の作成は指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業所)と契約し依頼することもできます。
作成料は全額が保険給付され、自己負担はありません。
施設サービスを利用する場合
特別養護老人ホームや老人保健施設などへ直接お申し込みください。
施設と契約して入所すると、施設でサービス計画を作成し、このサービス計画に基づきサービスを利用します。
サービスの利用と利用者負担
居宅サービスは、ケアプランに基づいてそれぞれのサービス事業者と本人が契約を結びサービスを利用します。サービスを利用したら、原則として費用の1割を事業者に支払います(残りの9割は保険から事業者へ支払われます)。
また、1ヶ月に支払った利用者負担が一定の上限額をこえた場合、申請により払い戻されます(該当になる方には町から通知が届きます)。
暫定サービスの利用
要支援・要介護の認定は、申請日にさかのぼって有効となります。申請時にすぐサービスが必要な場合は保健介護課にご相談ください。
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
保健介護課
TEL:
0985-75-9423
メールアドレス:
[email protected]
|
健康・福祉の情報
- 【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度非課税世帯への3万円給付について
- 活き行きバスカードについて
- 特別児童扶養手当
- 障がい児福祉手当
- 特別障がい者手当
- 子ども・子育て支援事業計画
- 社会福祉協議会
- 共生・協働 「地縁による団体」の法人化取得について
- 結婚新生活支援事業
- 国民健康保険
- 健康づくり・予防
- 母子保健
- 介護保険
- 高齢者福祉
- 地域包括支援センター
- 後期高齢者医療
- 児童福祉
- 障害者福祉
- 生活保護
- その他
- 重要なお知らせ