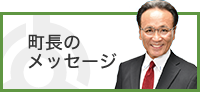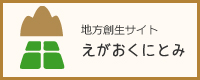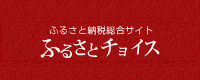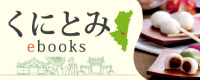定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われ、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方へは、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として令和6年9月以降に支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、令和6年分の所得情報が確定したことに伴い、昨年の調整給付金に不足額が生じた方、または定額減税の対象外で、かつ住民税非課税・均等割のみ課税世帯向け給付金の該当ではなかった方に給付金の支給を行うものです。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日時点での住民票所在地)が国富町の方で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のいずれかに該当する方が給付の対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
◇不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で
差額が生じた方に対して、その差額(1万円を最小単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)
を支給します。
【対象例】
〇令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が
少なくなった場合
〇子どもの出生等により令和6年中に扶養親族等が増加し、所得税分の定額減税可能額が増加した場合
〇当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度個人住民税分所得割額が減少した場合
※注意事項
・定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方、
また、所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方は、対象外です。
◇不足額給付Ⅱ
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方を対象とし、原則として4万円(定額)を支給します。
(ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入した方については、3万円)
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として
定額減税の対象外である
(2)税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外である(青色事業専従者・
事業専従者(白色)や令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る
合計所得金額が48万円を超える者)
(3)低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
(※1) 低所得世帯向け給付とは、以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
【対象例】
〇上記の支給要件をすべて満たす青色事業専従者や事業専従者(白色)
〇上記の支給要件をすべて満たす合計所得金額48万円超の方
支給額
1.不足額給付Ⅰに該当する方
定額減税しきれない額(※2)-令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
(※2)定額減税しきれない額とは、以下の(ア)と(イ)の合計額を1万円単位で切り上げた額
(ア)令和6年分所得税の定額減税しきれない額 (0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等))-令和6年分所得税定額減税済額
扶養親族等:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(イ)令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※3) (0円以下の場合は0)
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
扶養親族等:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(※3)個人住民税分の定額減税しきれない額に関して、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等が
ない場合は金額に変更はありません。
2.不足額給付Ⅱに該当する方
原則一人当たり4万円を上限
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
手続き方法
1.「支給のお知らせ」が届いた方
特に申請等の手続きは必要ありません。お知らせ文書に記載している口座に自動で振込みます。
※支給口座は、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)と同じ支給口座になります。
2.「支給確認書」が届いた方
給付金の申請手続きが必要です。
「補足給付金(不足額給付分) 支給確認書(提出用)」が届きましたら、支給確認書の内容を確認し、
必要事項を記入した上で、以下の必要書類を添えて、同封返信用封筒にてご返送ください。
(1)本人(代理人)確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
(2)口座情報が確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード)の写し
3.本給付金の受け取りを辞退される方、振込み口座を変更される方
・本給付金を辞退される方は下記届出書にご記入のうえ国富町税務課までご提出ください。
(様式第6号)補足給付金受給辞退の届出書.pdf
・給付金の振り込み口座を変更される方
(様式第7号)補足給付金支給口座登録等の届出書.pdf
4.申請が必要な方
下記のいずれかに該当する方で、給付金を受けるには申請手続きが必要ですので国富町税務課へ
お問い合わせください。
〇令和6年1月2日以降に国富町へ転入した方(「支給確認書」が届いた方は「手続き方法2」の
申請手続きが必要です。)
〇専従者(本町において対象要件の確認ができない場合)※
〇令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税に
おいて専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方 ※
〇令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度
個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の
対象となった方 ※
〇令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち、
本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方 ※
※非課税世帯等向け給付金の対象世帯に該当する方を除きます。
手続き期限
本給付金の手続き期限は、令和7年10月31日(金)【消印有効】です。
※期限までに手続きされない場合、支給できません。
※提出書類の受付後、概ね3~4週間後を目途に支給します。
※申請に不備(添付書類の不足等)がある場合は不備が補正された後の支給手続きとなります。
※振込日が決まり次第、個別に通知します。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座情報)・キャッシュカード・暗証番号の搾取」に
ご注意ください。
国富町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ショートメッセージ(SNS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に
ご相談ください。
関連リンク
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
税務課 賦課係
TEL:
0985-75-9404
メールアドレス:
[email protected]
|
- 重要なお知らせ